

2:29、起床。
未明どころか深夜と言って良い時間ですが、
今日の行程はとにかく長いのです。
最後息も絶え絶えになっていた剱岳第2日目(2020/9/21)が
距離9.3km、累積標高上り1,220m下り1,267m、
コースタイム9時間15分(YAMAP等倍)だったのに対し、
今日は距離11.7km、累積標高上り2,342m下り844m、
コースタイム9時間35分という長丁場。
東大ワンゲル部の山行では
常念山脈縦走第1日目(距離13.1km上り2,276m、2019/10/5)や
大峯北奥駈道第1日目(距離22.1km上り2,364m、2013/9/7)みたいな
もっと頭のおかしい日もありましたが、
大学登山部の基準を社会人登山部に持ち込む訳にはいかないので…
そう言うなら何故そんな行程を組んでしまったのか?
それこそが南アルプス南部に登山者が少ない理由その2、
山小屋の少なさです。
登山者が少ないからこそ山小屋も少なくなるので、
鶏が先か卵が先かという話ではありますが。
2時間も歩けば次の小屋が現れる北アルプスとは違い、
南アルプス南部は避難小屋を除くと
基本的に小屋から小屋まで6時間は掛かります。
流石に11.7kmの間に小屋が一つも無い訳ではなく
1つだけ中間に小屋があるのですが、
そこは予約合戦に敗れて予約出来ませんでした…

まだ空が白んでもいない3:20に出発。
梯子になりかけている急角度の鉄階段から入山します。
ここから明後日までは下界から隔絶された山上の人間になります。

現在登っている大倉尾根こと赤石岳東尾根は
大倉喜八郎が卒寿祝いで整備させたあの登山道で、
初めの内は樹林帯なので日が出ていようが眺望はありません。
しかも、この区間は急登で有名なんだよな…

林業で拓かれた山なだけあって林道とも交差します。
南アルプスの林道はもう殆ど荒廃する一方ですが。
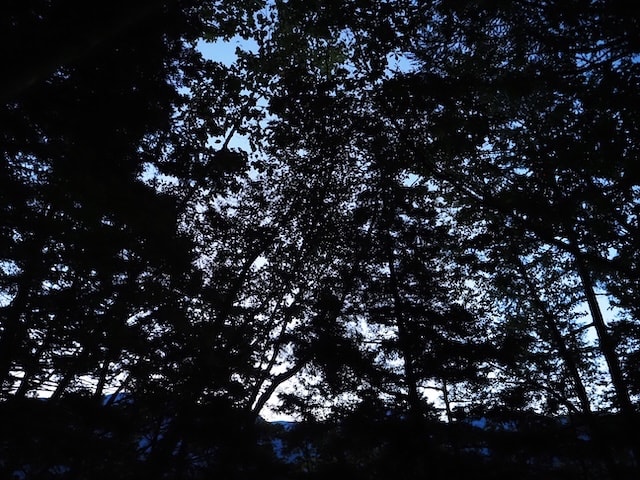
急登と格闘していたら
いつの間にか空が白んでいました。

椹島から赤石小屋までの中間地点だという樺段に到着。
赤石岳山頂じゃなくて赤石小屋までの中間地点なのか…
ここまで2時間だからそんなものか。

「最後の難関」という案内のあった歩荷返し。
難関…?
岩が所々露出していてちょっと歩き難いと言えばそうだけど…
これくらいで踵を返してしまう歩荷は根性無さ過ぎでは。

クソザコ歩荷は返しても我々を返すには及ばず、
サクッと歩荷返しも通過。
赤石小屋まで後少し!

8:06、赤石小屋に到着。
ここが予約合戦に敗れて予約出来なかった山小屋です。

ここへ来て遂に赤石岳の展望が開けました!
何と堂々たる山容。
流石は南アルプス(赤石山脈)の盟主です。
…今日中にあそこまで登って、更に次の小屋まで歩くのか。

それはそれとして、大展望の中で冷えたサイダーを頂きます。
うーん、最高!
炭酸飲料は深山で飲んでこそ輝きます。
…ステマみたいになっているかな?

衝撃の事実として、ここはまだ中間地点です。
しかも、今日一日の行程の中間地点ではありません。
赤石岳までの中間地点なのです。
深いなぁ〜、南アルプス!
休憩も程々に再出発です。

振り返ると雲海から顔を出した富士山が。
堂々たる姿のようであり、
今直面している巨大山塊南アルプスと比べるとちっぽけにも見えたり。
この展望を望める平場はその名も富士見平です。

まるで富士山と張り合うかのように構える赤石岳。
左のピークが赤石岳、右のピークが小赤石岳です。

あまりに大きく広がっているので
広角レンズでも1枚に収め切れませんが、
右にぐっと振った遥か向こうにあるのが
左から荒川中岳、悪沢岳(東岳)、それに力瘤のような千枚岳。
…あの千枚岳の更に左にある千枚小屋までが
明日の内に歩き切らねばならない道のりです。

まあ、一見とんでもない距離に見えても
意外と人間歩き切れるものです。
一歩一歩目の前の道を進んでいくことに集中します。
割と岩場チックで険しい道だな…

一様に撓って弧を描いた木々。
南アルプスもこの標高まで来ると結構雪深いのでしょうか。

標高2,700mを越えて遂に森林限界を迎えました。
9月中旬でもまだまだ暑い静岡県。
遮る物無く照り付ける陽射しが体力を奪います。

水場って何処だよ…
カラカラに枯れています。
赤石小屋で十分補給していたので大丈夫ではありますが。

着実に稜線が近付いてきています。
北アルプスとは違う、如何にも脆そうな稜線です。

富士山に見守られながら歩く隊。

入山から8時間で稜線に到達しました!
ここから先明後日まで満喫する予定の南アルプス主稜線です。

まずは重い荷物を分岐点にデポして
赤石岳を討ってしまいましょう。

11:58、赤石岳(標高3,120m)登頂です!
日本第7位の高峰であり、
標高3,015mの立山(2019/7/20)、標高3,193mの北岳(2023/9/2)に次いで
僕にとって人生で3座目の3,000m峰です。
ちなみに、ここに設置されている一等三角点は
日本で最も高い位置にある一等三角点だったりします
(富士山山頂にあるのは二等三角点、北岳山頂は三等三角点)。

およそ3,000m峰とは思えぬ静寂の山頂。
代償として辛く長い道を歩き切る必要があるとはいえ、
この天空の世界を独占出来るとは何とも贅沢な山です。
この先(南)は更に登山者の少ない山域になりますが、
今回は立ち入りません。
あっちへ行ってしまうと下山が滅茶苦茶大変になるので…

ただ、赤石岳山頂直下には赤石岳避難小屋があるので寄ってみます。

赤石岳避難小屋は静岡県営の有人小屋。
避難小屋らしからぬ小綺麗な佇まい。
緊急時以外宿泊禁止というのが一般的な避難小屋のルールですが、
ここは事前予約制で普通に宿泊が出来ます。

素泊まりのみの上に定員はたったの10人ですが。
売店もペットボトル飲料と菓子パンくらいしか売っていません。
まあ、本来避難小屋に売店があること自体異例ですが。
ここ、コースタイム的には宿泊に凄く丁度良い位置ではあるんだよな…

定員50人の赤石小屋さえ予約合戦に敗れたのに
定員10人の小屋の予約が抑えられているはずもないので、
たっぷり40分赤石岳山頂を満喫したら登山再開です。
一気にガスって来たな…
赤石岳山頂がギリギリ晴れていて本当に良かった。

小赤石岳(標高3,081m)を越えて稜線を進みます。
宿泊地はまだまだ先です。

赤石岳の一帯から下って次の山塊への登り返しとなる鞍部、
大聖寺平までやって来ました。
ガスっていると道迷いしそうな広い鞍部です。

こんな場所にも特殊東海製紙の標識が立っていました。
ここまで標識を設置しに来た社員の方も大変ですね…
流石に委託したのかな。

ここから登山道はトラバースになります。
疲労で足運びを間違えて足を挫いたりしないよう注意します。
何てったってどちらを向いても下山まで10時間は掛かるような場所。
怪我は許されません。
そろそろ日も傾いてきた様子があるけど、
小屋はまだだろうか…

あっ!あれはーッ!

14:41、入山から11時間以上も掛けて遂に辿り着きました!
如何なる登山口から目指しても優に10時間以上を要する
日本でも指折りの遠い山小屋、荒川小屋です!!

荒川小屋は南アルプスの中で最も歴史の長い山小屋の一つ。
稜線(長野-静岡県境)の東斜面(静岡県領)に位置していながら
人里の近さから元々は長野県側の大鹿村が管理していました
(現在、大鹿村から登る小渋川ルートは
崩壊が進んでいる上に渡渉が多いのでバリエーションルート扱い)。
それが平成8年に他と同じく静岡県営の小屋となり、
更に近年建て替えられたのかとても新しい印象を受ける小屋です。

荒川小屋の北には、小屋の名前になっている
荒川岳が重厚感のある山容で構えています。
明日はあそこを登るのか…

明日はあそこを登るのか…
そりゃあ見ようとしなくても見えちゃうよね…
急斜面をあんな無理くり稲妻状に這い登っていく登山道…

まあ、明日の事は明日やるとして
今日のところは11時間の闘いの疲れを癒しましょう。
荒川小屋はこの立地ながら何とケーキを頂けるという神小屋です。
最高過ぎる。

順光になってやけに近く見えるようになった富士山も、
大井川の向こうの稜線(静岡-山梨県境)越しに
僕等に労いの言葉を掛けてくれているかのようです。

談話室で次の登山について話し合ったりしていたら
いつの間にか17時になっていたので夕食。
荒川小屋の味噌汁は卵焼きが入っているのが特徴?

夜は邪魔な光が一切無い状況で天体観測をしたりしてから、
明日以降に備えて早めに寝ました。



コメント