
刻一刻と引っ越しが迫ってきています。
今の内にやっておくべきことは何か残っていないか…
そう言えば…

引っ越しすると大分遠くなる成田にやって来ました。
今も別に全然近くはないのですが、
タイヤは交換前に擦り減らしておいた方がお得かと思って。
成田国際空港の南隣にある航空科学博物館です。
ここの目玉は本格的なフライトシミュレーター。
開館と同時に受け付けをして枠を抑えました。
高がシミュレーターでしょ?と思われるかも知れませんが、
フライトシミュレーターはパイロットの訓練の要であり、
事故調査では未知の挙動を再現するのにも使われるなど
極めて緻密な物理演算の下に成り立っているのです。
車校のなんちゃってシミュレーターとは訳が違います。
果たして、セスナの操縦経験(2023/4/2)は通用するのか。

という訳で、まずはボーイング777から。
セスナ172とボーイング777の最大の違いは
(レシプロエンジンの)プロペラ機かジェット機かという点。
これが操縦にどう効いてくるかというと、
端的に言って反応が非常に鈍くなるんですね。
エンジン特性以前の問題として
そもそも重量が300倍以上違うというのもあって、
レバーを動かすと一瞬で反応するC172と違い、
B777はスロットルレバーや操縦桿を動かしてから
実際に反応するまでに数秒のラグがあります。
このラグの所為で操縦が滅茶苦茶やりにくい!
軽い未来予知みたいな能力を求められます。
では、B777の操縦はC172よりも遥かに難しいかというと
一概にそうとは言い切れなくて、
重量というのは安定性を高める利点もあるんですね。
風に振られることはずっと少なくなるので
ちょこまか微調整をするのは避けられますし、
何よりB777には自動操縦装置があります。
ぶっちゃけ巡航時にする操作はダイヤルの調整だけです。
着陸も自動操縦で出来たりしますが、
そこまでやると体験の意味が無いので離着陸は手動で。
3年前(2020/1/13)のF-1シミュレーターでは
時間内に着陸させることが出来ませんでしたが、
今回は教官の助けを得つつ上手く着陸させることが出来ました。

ジェット旅客機の操縦特性を掴んだら、
今度は更に本格的なB737-MAXのシミュレーターに挑戦。
このシミュレーターは離陸体験が出来ず着陸だけです。
MCAS絡み…と勘繰るのは考え過ぎだろうか。
B777ではスロットル操作を教官に助けてもらいましたが、
今度は全部自力で手動操縦して着陸させられました。
ILS(計器着陸装置)は偉大。
実に面白かったです。
今度セントレアのシミュレーターもやってみようかな?

シミュレーター以外に普通の展示もあるので見ます。
大体メーデーで見たことのある内容…
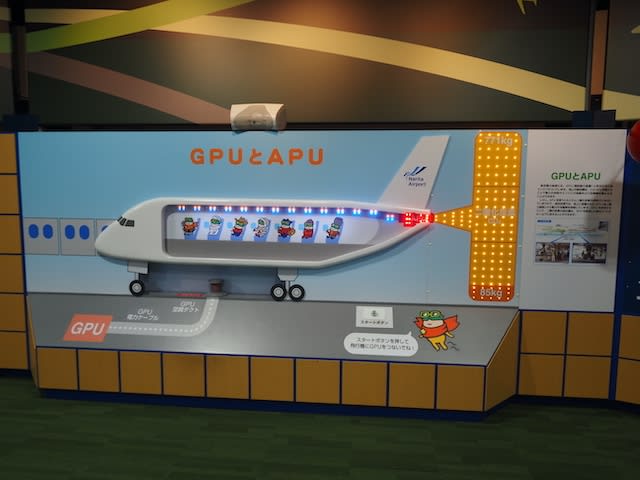
と思っていましたが、GPU(地上動力装置)は知りませんでした。
これが原因の航空事故は聞いたことがないので…
今はAPU(補助動力装置)じゃないんですね。

最上階の展望台からは成田国際空港A滑走路から
南向き(16R)に離陸していく機体を眺められます。

あと、これは正確には別の施設なのですが、
航空科学博物館の南隣には空と大地の歴史館という
成田闘争(三里塚闘争)の資料館もあります。
航空科学博物館の陰に隠れがちですが、
こちらも覗いてみます。

想像以上に過激な運動だったんですね…
実質内戦では。
東峰十字路では30人の警官隊が数百人の学生にタコ殴りにされ、
3人の警官が殉職するという事件まで起きたとか。

というその東峰地区にやって来ました。
嘗ての壮絶な闘争を受けて
沿道は全て高いスチール塀に囲まれ、
滑走路の様子は一切窺い知れないようになっています。

そんな物々しい東峰地区の中で、
1ヶ所だけ観光客の集う場所があります。

それがこの東峰神社。
B滑走路南端(34R)の目の前に鎮座する神社で、
周囲360°を空港敷地に囲まれた異常な立地にあります。
ここはその昔反対派がB滑走路の延長を阻止する為に
拠点として用いていた過去があり、
近年まで「訪問するだけで職質されるスポット」として
名を馳せていた曰く付きの場所なのですが、
最近では「飛行機を間近に見られる珍しい神社」という
インスタ映えスポットのような扱いに変わっており、
職質を受けることも殆ど無くなったとか。

それでも、金網の向こうには見張り小屋があり、
24時間体制で不審者が居ないか監視しているようです。
なお、神社の上を巨大な飛行機が飛んでいく
映える写真を撮りたい場合は北風の日に来ましょう。
今日はほぼ無風なので反対側の16Lからしか着陸しません…

成田国際空港の光と影を見学出来たら、
道の駅発酵の里こうざき、水の郷さわら、たまつくりを巡って
桜土浦ICから多摩に帰りました。



コメント